読む力 – 現代の羅針盤となる150冊
著者:松岡 正剛、佐藤 優 …
| このお二人の本の読み方、こんなに深いのにこんなにたくさん・・・でもそれがプロの読書なんでしょうね。非常に参考になります。こういった人たちの考え方に触れられるのは本当に楽しいです。(Inobe.Shion) |
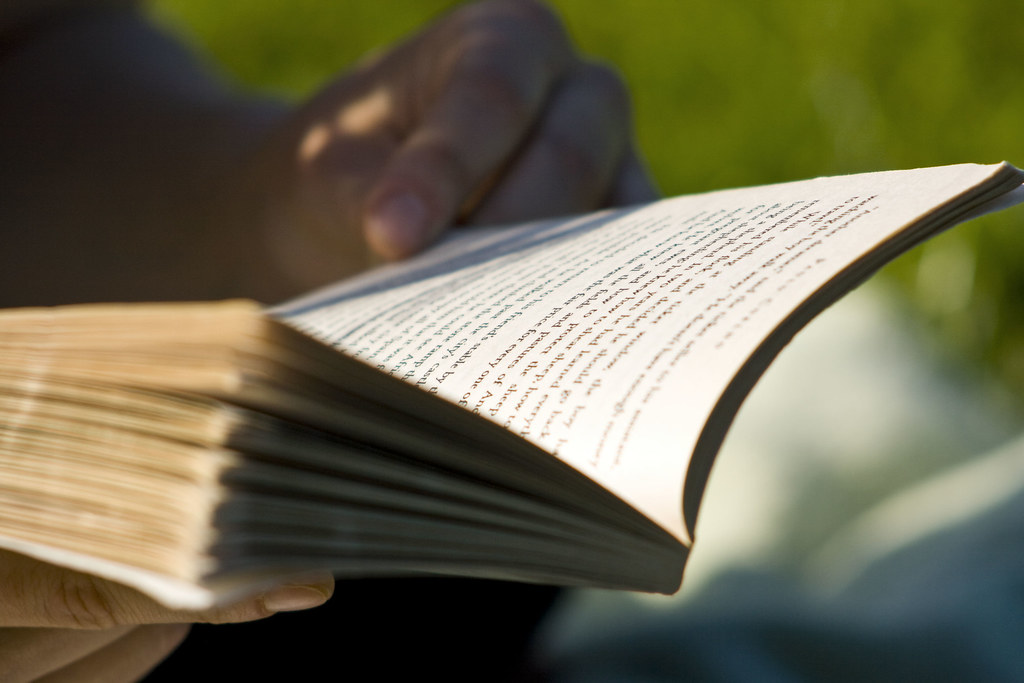
| 内容紹介
松岡氏、佐藤氏、初の対論集! ◎内容例 【目次】 内容(「BOOK」データベースより) 松岡氏、佐藤氏、初の対論集!既存の価値観がすべて費えた混沌の時代に、助けになるのは「読む力」だと二人は言う。「実は、高校時代は文芸部でした」という佐藤氏の打ち明け話にはじまり、サルトル、デリダ、南原繁、矢内原忠雄、石原莞爾、山本七平、弘兼憲史まで。混迷深まるこんな時代にこそ、読むべき150冊を提示する。これが、現代を生き抜くための羅針盤だ。 |
まえがきにある松岡さんの言葉、グッときます。
| 「読む力」には三つの「A」がすこぶる有効である。アナロジー、アフォーダンス、アブダクションだ。その本から何を類推できるのか、何を連想したかということ(アナロジー)、その本によって何が制約されたのか、攻め込まれたのかということ(アフォーダンス)、その本によって何を前方に投げられるのか、どんな仮説がつくれるのかということ(アブダクション)、この3つだ。この3つのAが本を読むたびに立体交差をするように動けば、「読む力」は唸りをあげていく。読むとは、従属することではない。守って破って離れることだ。読むことによって、読者はもう一冊の本を編集できるのである。(p.7) |
本を読むことによる「守破離」。深いです。そもそも「守」となり得るまで深く入り込めるかが問題です。
| 読ませるためには、読者の身体とか、表情とか、そのときの目つきとかが、まざまざとイメージできるような作り方をしないと、駄目だと思うのです。本に著される思想とか知識とかというものは、リフレクターが介在したり、何かと鏡像関係を結んだりすることで、大きく変わってくるものです。「伝えたい相手がいる」「読者の顔が見える」ことによって、初めてブラウザーを的確に働かせることができる。伝えたい相手がいないメディアは、やっぱりつまらない。(pp.51-52) |
私もいずれは本を出版したいという気持ちはあるのですが、この部分は大事ですよね。発信したいことがあるのはもちろんですが、受け取ってほしい人に対して、それをチューニングして届けないと正しく受け取ってくれないということは、本だけでなくコミュニケーションにおいてはすべて当てはまることでしょう。
| 戦後の思想論壇はマルクス主義を評価したサルトルが唱えた実存主義が、ソ連崩壊とともに後景に退き、物事を相対化する構造主義のレヴィ=ストロースが登場します。レヴィ=ストロースは、近代を相対化はしましたが、「ブリコラージュ」といって、思想を部分的に修正、編集して活用することには意義があると考えていた。メルロ=ポンティからロラン・バルトくらいまでは、この方法としてのブリコラージュが生きていた。ところが、その後に現れたジャック・デリダ以降になると完全に大きな物語が消えて、すべてを入れ替えよという脱構築状態になった。ポストモダン思想ですね。ヨーロッパはしばらく方法を見失ったと思うんです。共通の通貨ユーロは導入したけれど、EUは結局、イギリスが離脱することになりました。(p.62) |
もともとは、レヴィ=ストロースが言った「ブリコラージュ」もカルチュラル・スタディーズではもう少し拡大解釈された「ブリコラージュ」として展開していったようです。
| 最近の論壇には引き算の思想がありません。世阿弥や千利休がやってきたことは、引き算して、何かを極めるということです。枯山水のように、「水を感じたいから、水を抜く」という超矛盾の極致に向かうような思想がない。(p.77) |
佐藤さん曰く「自分のイメージとしては、大きな木があって、それをノミで削っているだけなんです」と。
それにしても足すことはいくらでもできますが、既にブラッシュアップされているとするとそこから抜いていくというのは非常に難易度が高いですが、やりがいのあることだと思います。
そして第3章から第4章にかけては秀逸です。何というのでしょうか、自分の無知を痛感させられます。読むべき本を紹介してくれているのですが、第3章で「日本を見渡す48冊」、第4章で「海外を見渡す52冊」として計100冊が紹介されているわけですが、どれもこれも重要なのはよくわかるのですが、どれから読んでいいか・・・。
どれもこれもそう簡単に読み解けるものでもないでしょうし、どれからいくのがいいんでしょうかね。
そんなことを考えながら、読んでいますと、答えは次の章に。
次の章に「通俗本50冊」が紹介されています。ここに紹介されているのは非常に質の高い書物です。ここのこの通俗本から土台を固めていうのがよさそうです。
それにしても第3・4章は、松岡さん、佐藤さんは簡単に語られていますが、この知識の広さ、深さ・・・すごすぎて言葉になりません。
少しでも彼らに近づけるように質の良い本を効果的に読み進めていきたいと思います。
